口内炎とは、口腔粘膜の比較的広範囲の炎症状態である。その症状により、①カタル
性、②潰瘍性、③壊死性、④アフタ性などに分類される
●病型分類
1)カタル性口内炎
カタル性口内炎とは、粘膜の表在性の発赤を主体とする口内炎をい
う。
2)壊死性口内炎
急性壊死性潰瘍性歯肉炎、壊死性潰瘍性歯周炎および壊死性口内炎はあわせて、壊死性歯肉口内炎と呼ばれている。嫌気性菌を主体とする細菌感染症である。
更年期に多く発症し、歯肉痛(接触痛、自発痛)、歯間乳頭の壊死あるいは潰瘍形成、歯肉出血を主な特徴とする。口臭や病変部の偽膜形成も認められる。病状が進行すると発熱、リンパ節の腫大、全身の倦怠感を伴うことがある。病状の進行をみると、
1.歯間乳頭先端のみに壊死形成、
2.歯間乳頭全体が壊死、
3.歯肉縁に壊死が拡大、
4.付着歯肉に壊死が拡大、
5.隣接粘膜へ壊死が拡大、
6.歯槽骨が露出して骨も壊死、
7.頬部皮層に壊死が波及し穿孔を来す。
発症因子としては、
①壊死性歯肉口内炎の既往歴、
②口腔衛生不良
③睡眠不足、
④種々のストレス、
⑤栄養不良、
⑥全身性疾患、
⑦大量の飲酒、
⑧喫煙、
⑨年齢(20歳代)が重要視されている。
治療は、抗菌薬療法に含嗽療法を併用する。経口摂取困難があれば
栄養管理も行う。
3)アフタ性口内炎
アフタとは粘膜における直経1~10mm程度の円形ないし類円形の境界明瞭な比較的浅い潰瘍で、潰瘍面は灰白色の偽膜に被われ、周囲に紅壼を伴うものをいう。症状名であり疾患名ではない。
再発性アフタ
アフタが1~多数個、数日から数カ月の間隔で定期的あるいは不定期的に再発を繰り返す場合を再発性アフタと呼ぶ。原因は不明である。
好発初発年齢は10~20代であるが、壮年期にも好発する。
潰瘍は可動性粘膜(非角化粘膜)に発症することが多いが、まれに歯肉、舌背粘膜、硬口蓋粘膜にもみられる。潰瘍は接触痛、自発痛などの瘤痛を伴う。潰瘍が多発すると経口摂取が困難となり、嚥下困難も
みられる。再発性アフタは疾患名であるが、アフタ性口内炎は症状名のため同義語ではない。
再発性アフタの臨床的病型分類
小アフタ型、大アフタ型、ヘルペス型と3つの病型がある。再発時には、通常は1つの病型のみであるが、2つの病型が共存することもある。さらに、常に同じ病型を繰り返すとは限らず、他の病型に変化
することもある。
診断は病歴と臨床所見に基づいて行う。潰瘍のサイズ、潰瘍の数、潰瘍の部位や範囲などにより、痙痛の強さが異なる。たとえ1個でも、部位によっては瘻痛が強く、経口摂取困難や嚥下困難を伴うこともあ
る。瘤痛の強さ、嚥下痛の有無および経口摂取量の程度などからその重症度を判定し治療を行う。
理想とする治療は、再発の予防、再発回数や再発時の潰瘍数の減少などであるが、現時点ではそれらに対する有効な治療法は確立されておらず、疼痛の緩和と潰瘍の治癒促進を目標とする局所療法による対
症療法が主となる
4)ベーチェット病
再発性口腔内アフタはベーチエツト病の初発症状のなかで最も多く、経過中ではほぼ全例に認められる。臨床的にはベーチェット病におけるアフタと再発性アフタとの鑑別は困難である。
局所療法
■含嗽剤(抗炎症作用、肉芽新生と上皮形成促進作用)
・アズレンスルホン酸ナトリウム・炭酸水素ナトリウム
【含嗽用ハチアズレ穎粒】
・アズレンスルホン酸ナトリウム(水溶性アズレン)
【アズノール⑧細粒・錠・ガーグル・うがい液】
■トローチ剤
・アズレンスルホン酸ナトリウム【アズノールST錠口腔用
■口腔用軟膏剤
・デキサメタゾン【アフタゾロン口腔用軟盲0.1%、デキサルチン
口腔用軟膏
・トリアムシノロンアセトニド【ケナログ口腔用軟膏
■その他の口腔用薬(口腔粘膜付着剤
■副腎皮質ホルモン剤による含嗽療法
・デキサメタゾン【デカドロンエリキシル
全身療法
■副腎皮質ホルモン剤内服【デキサメタゾン
再発性アフタの薬物療法
潰瘍数が少なく付着可能な部位の場合
アフタゾロン口腔用軟膏
含嗽剤
含嗽用ハチアスレ穎粒:1回1包を約100mLの水または微
温湯に溶解し、1日数回含嗽
アズノール含嗽液
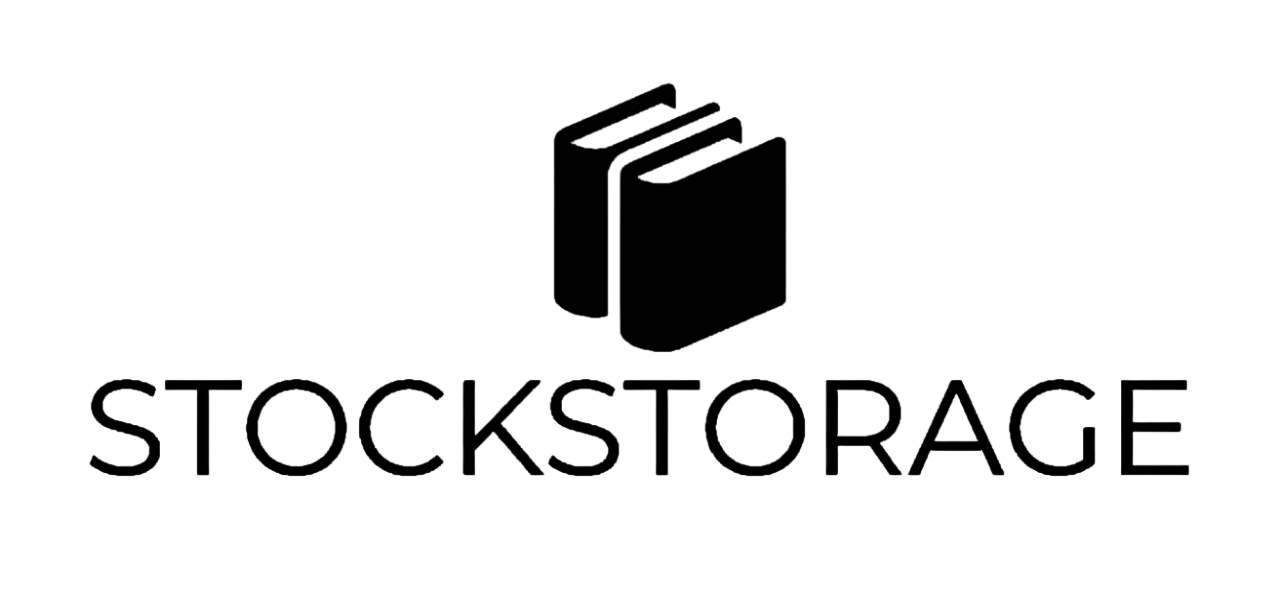

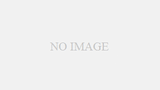
コメント